このページの目次
「AIで記事を量産したら順位が下がった…」その原因は?
「AIを使えば、専門的な記事も効率的に作成できるはず」
そう考えてAIライティングツールを導入したものの、期待とは裏腹に、ウェブサイトの検索順位が思うように上がらない、あるいはかえって下がってしまった…。もし先生がこのような状況に陥っているのであれば、それは決して珍しいことではありません。
なぜ、このような事態が起きてしまうのでしょうか。その根本的な原因は、Googleが掲げる「ユーザーファースト」という理念と、士業の方々が扱うYMYL(Your Money or Your Life)という領域に課せられた、極めて厳格な品質基準にあります。
この記事では、AIでYMYL記事を作成する際に潜むリスクと、その対策について、士業専門のWebマーケティングに長年携わってきた専門家の視点から、具体的な「処方箋」を提示します。単なるツールの使い方ではなく、AIと共存し、Googleからもユーザーからも真に評価されるコンテンツを生み出すための本質的な考え方をお伝えします。
GoogleがAI生成コンテンツを低評価する本当の理由
まず、最も重要な点を押さえておきましょう。Googleは「AIが生成したから」という理由だけでコンテンツを低評価するわけではありません。Googleが問題視しているのは、「コンテンツの品質が低く、ユーザーにとって価値がないこと」です。
Googleの公式な見解でも、AI生成であるかどうかに関わらず、高品質なコンテンツであれば評価の対象となることが明言されています。問題は、AIを使って「検索順位を操作すること」を主な目的として作られた、質の低いコンテンツです。
例えば、以下のようなコンテンツは、たとえ人間が書いたものであっても評価されません。
- 情報の正確性が担保されていない、あるいは誤った情報が含まれている
- 独自性や専門的な知見がなく、どこかで読んだことのあるような一般的な内容に終始している
- ユーザーの悩みを本当に解決しようという意図が感じられない
AIは驚くべき速さで文章を生成できますが、その反面、上記のような「質の低いコンテンツ」を意図せず生み出してしまうリスクも抱えています。「AIを使えば楽に上位表示できる」という考えは、Googleの理念とは相容れない、危険な誤解であると認識する必要があります。
参考:Google Search’s guidance on using generative AI content
特にYMYL領域でAI活用が危険な理由
中でも、士業の方々が扱う法律、税務、登記といったテーマは、Googleによって「YMYL(Your Money or Your Life)」、つまり人々の幸福、健康、経済的安定、安全に大きな影響を与える可能性のある領域として、特に厳しく評価されます。詳しくは【士業のための最新SEOトレンド解説・番外編】YMYL領域とは?弁護士・司法書士・税理士・行政書士が知っておくべきSEOの前提知識でも解説していますが、この領域では情報の正確性が人の人生を左右しかねません。
例えば、相続に関する不正確な情報が原因で家族間のトラブルに発展したり、許認可に関する誤った知識が事業の存続を脅かしたりする可能性もゼロではありません。
だからこそ、GoogleはYMYL領域のコンテンツに対して、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)という厳しい品質基準を設けています。現行の法制度・実務運用においてはAI自身が法的責任を負うことはできないため、最終的な確認・責任は人間の専門家(記事作成者・監修者)が負う必要があります。したがって、AI出力は専門家による検証・監修を前提に使用してください。安易にAIに頼った記事作成は、この最も重要なE-E-A-Tの根幹を揺るがしかねない、大きなリスクを伴うのです。

あなたの記事は大丈夫?E-E-A-Tを満たさないAI記事の特徴
ご自身のウェブサイトに掲載されている記事を、一度客観的に見直してみましょう。もしAIを活用して作成した記事に以下の特徴が当てはまる場合、Googleから低品質と判断されている可能性があります。一つずつ、チェックしてみてください。
【チェックリスト1】情報の正確性と一次情報の欠如
AIは、学習したデータに基づいて「もっともらしい」文章を生成することは得意ですが、その情報が本当に正しいか、最新のものかを常に保証してくれるわけではありません。特に、法改正や新しい判例など、情報の鮮度が重要な士業の分野では、AIが古い情報を参照してしまう「ハルシネーション(もっともらしい嘘)」のリスクは無視できません。
また、AIが生成する文章は、インターネット上の様々な情報を平均化したような、当たり障りのない内容になりがちです。これでは、他のサイトとの差別化は図れません。
ここで重要になるのが「一次情報」です。一次情報とは、先生ご自身の実務経験に基づく見解、独自の調査データ、実際にご依頼者様から受けた相談事例(プライバシーに配慮したもの)などを指します。こうした情報は、他の誰にも真似できない価値を持ち、E-E-A-Tにおける「経験」や「信頼性」を飛躍的に高める源泉となります。
【チェックリスト2】執筆者の経験・専門性が感じられない
「この記事は、本当にこの分野のプロが書いたのだろうか?」
読者やGoogleにそう思われた瞬間に、記事の信頼性は失墜します。当たり障りのない一般論に終始し、具体的な事例や、先生自身の個人的な見解・考察が全く含まれていない記事は、まさにその典型です。
近年、GoogleがE-E-A-Tの中でも特に「Experience(経験)」を重視するようになったのは、ネット上に情報が溢れる中で、実際にその道を歩んできた人でなければ語れない「生きた知識」にこそ価値があると考えているからです。
AIが生成した文章は、いわば「知識の要約」です。そこに先生自身の経験というフィルターを通した解釈や、ご依頼者様への想いを加えることで、初めて読者の心に響く、血の通ったコンテンツへと昇華されるのです。
【チェックリスト3】サイト全体の信頼性・権威性の不足
Googleは、記事単体の品質だけでなく、その記事が掲載されているウェブサイト全体が信頼に足るかどうかを評価します。どれだけ素晴らしい記事を書いても、サイト全体の信頼性が低ければ、その評価は限定的なものになってしまいます。
具体的には、以下のような点を確認してみてください。
- 運営している事務所の名称、所在地、連絡先が明確に記載されているか?
- 執筆者や監修者である先生のプロフィール(経歴、資格、得意分野など)が顔写真付きで掲載されているか?
- プライバシーポリシーや、お問い合わせフォームは設置されているか?
- サイトのデザインが古かったり、スマートフォンで表示が崩れたりしていないか?
これらは、ユーザーが安心してサイトを利用するための「土台」です。この土台がしっかりして初めて、個々の記事の専門性が正しく評価されるのです。
【処方箋】YMYLでAIと共存しE-E-A-Tを高める実践ステップ
では、具体的にどのようにAIと向き合い、E-E-A-Tの高いコンテンツを作成していけばよいのでしょうか。AIを「執筆の代行者」と考えるのをやめ、「優秀なアシスタント」として位置づけることが成功の鍵です。ここでは、私たちが推奨する3つの実践ステップをご紹介します。

ステップ1:AIは「壁打ち相手」と「構成案のたたき台」に使う
AIの最も安全かつ効果的な活用法は、記事の「企画・設計」段階で使うことです。AIは、思考の整理やアイデア出しのパートナーとして非常に優秀です。
例えば、対策したいキーワードをAIに伝え、以下のような作業を任せてみましょう。
- そのキーワードで検索する読者が抱えているであろう悩みを、多角的にリストアップさせる
- 想定される読者の悩みに答えるための、記事構成案を複数パターン作成させる
- 記事のタイトル案を10個ほど提案させる
このように、AIを「壁打ち相手」として活用することで、自分一人では思いつかなかった視点を得られたり、思考を深めるきっかけになったりします。あくまで人間が主導権を握り、AIが生成した「たたき台」を元に、専門家である先生の知見で最適な構成を練り上げていく。これが理想的な協業モデルの第一歩です。
ステップ2:一次情報と専門的見解で「血の通った文章」にする
AIが作成した骨子(構成案)は、いわば建物の設計図です。ここに、先生自身の経験という名の建材を使い、読者が安心して住める家を建てていく工程が、このステップです。
私たち株式会社アップラボは、士業の先生方のWeb集客を長年にわたりご支援する中で、「AIで記事を作っても、なかなか成果が出ない」という切実なご相談を数多く受けてきました。AIの普及により、誰もがある程度の品質の記事を簡単に作れるようになった今、その他大勢から一歩抜け出すために不可欠なのが、先生にしか書けない「一次情報」なのです。
こうした課題を抱える先生方に、AIが生成した文章に「先生自身の言葉」を加えていただくことの重要性を常にお伝えしています。例えば、過去の事例、ご依頼者様との対話で感じたこと、法改正に対する先生自身の見解などを盛り込むだけで、文章は驚くほど生き生きとします。AIが作った無機質な文章に、先生の経験と情熱という血を通わせることこそが、E-E-A-T対策の核心です。
ステップ3:専門家による「監修」と「最終ファクトチェック」を徹底する
記事を公開する前の、最後の砦が「監修」と「ファクトチェック」です。たとえ先生ご自身が執筆した場合でも、一度時間をおいて客観的な視点で見直すか、可能であれば事務所内の他の専門家にも目を通してもらうことを強く推奨します。
チェックすべき項目は多岐にわたります。
- 情報の正確性:記載されている法律やデータ、手続きは本当に正しいか?
- 情報の最新性:法改正など、最新の情報が反映されているか?
- 法令・広告規制の遵守:士業の広告ガイドラインに抵触する表現はないか?
- 表現の適切さ:読者に誤解を与えたり、不安を煽りすぎたりする表現はないか?
そして、誰がこの記事の情報の正確性を担保しているのかを明確にするため、記事の末尾やプロフィールページに監修者として先生のお名前と経歴を明記しましょう。この一手間が、読者からの信頼とGoogleからの評価を大きく左右します。

「AIアシスタント」との理想的な協業をツールで実現
ここまで、AIを「優秀なアシスタント」として活用し、先生の専門的な知見(一次情報)を加えてE-E-A-Tを高める3つのステップをご紹介しました。
しかし、多忙な先生方にとって、この「構成案の作成」や「AIが生成した文章のファクトチェックと追記」自体が、依然として大きな負担であることも事実です。汎用的なAIツールでは、士業特有の広告規制(コンプライアンス)への対応も不安が残ります。
こうした課題を根本から解決するために、私たち株式会社アップラボが独自に開発したのが、AIライティングプラグイン「OGAI(オーガイ)」です。
OGAI:先生の「最終チェック5%」で記事を完成させる専門家特化AI
OGAIは、一般的なAIライティングツールとは一線を画します。OGAIが目指すのは、AIが記事作成の95%を担い、専門家である先生には最も重要な「最終承認(残りの5%)」だけを行っていただく、理想的な「二人三脚」のワークフローです。
- 士業特化の設計:弁護士法などの広告規制ガイドラインを学習した「コンプライアンスAI」を搭載。意図しない表現リスクを自動で回避します。
- E-E-A-Tへの対応:検索上位サイトを分析して「勝てる構成」を自動生成。さらに先生の独自事例を組み込む「E-E-A-T注入AI」により、専門性と信頼性を最大化します。
- 圧倒的な時間短縮:数時間かかっていた記事作成が、わずか数分の最終チェックで完了。先生の貴重な時間を、本来の業務であるご依頼者様との対話に集中できます。
OGAIは、この記事で解説した「AIをアシスタントとしてE-E-A-Tを高める」というプロセスを、士業の先生方のために最適化したソリューションです。
YMYL領域のAI活用に悩んだら専門家にご相談ください
AIは、士業の先生方にとって強力な武器になり得ますが、特にYMYL領域においては、その活用法を誤ると大きなリスクを伴う「諸刃の剣」でもあります。
AIを安全かつ効果的に活用し、ウェブサイトを事務所の重要な情報発信ツールとして育てるためには、ツールの知識だけでなく、SEO、YMYL、そして士業の広告規制に関する深い理解に基づいた戦略が不可欠です。※成果は業種・コンテンツ・運用体制によって異なります。
もし、先生が「AIを導入してみたものの、うまく活用できていない」「何から手をつければ良いのかわからない」「自社のウェブサイトのE-E-A-T対策は十分だろうか」といったお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度、私たちサムライラボにご相談ください。
私たちは、単にウェブサイトを制作する会社ではありません。士業に特化した専門家として、先生の事務所の理念や強みを深く理解し、長期的な視点で資産となるホームページを育てるための戦略を共に考え、伴走するパートナーです。
士業のWeb集客・AI活用に関するご相談はこちらから、お気軽にお問い合わせください。



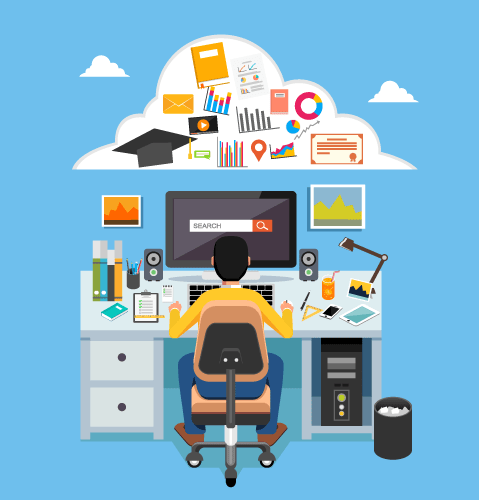
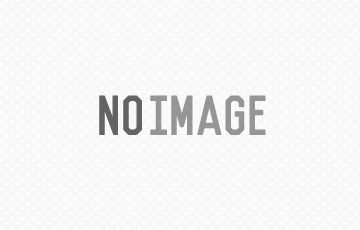

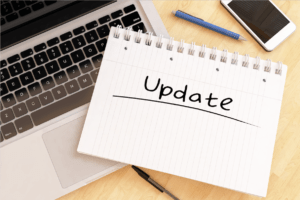



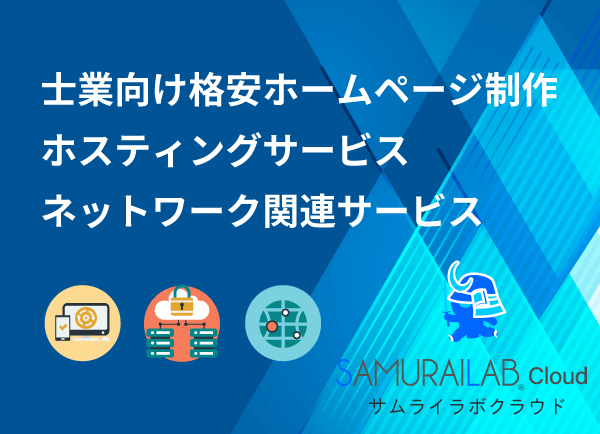




コメントを残す